
とちの木通り
とちの木通りと呼ばれるようになったのは昭和58年(1983年)からで、中ほどに上鷺宮区民活動センターがあります。この通り沿いには昭和初期から昭和62年(1987年)まで沢庵工場があり、直販もしていました。
閲覧数49



 なかの生涯学習大学
なかの生涯学習大学
なかの生涯学習大学が投稿した「地域資源マップ」の情報です
全90件
最終更新:219日前

とちの木通りと呼ばれるようになったのは昭和58年(1983年)からで、中ほどに上鷺宮区民活動センターがあります。この通り沿いには昭和初期から昭和62年(1987年)まで沢庵工場があり、直販もしていました。
閲覧数49

新青梅街道沿いに武蔵台小学校、北中野中学校、武蔵丘高校、が隣接しています。地元の人の熱意で実現したこの文教エリアは上鷺宮小学校、稔ヶ丘高校と併せ、地域の充実した教育環境を形成しています。
閲覧数61

寛政3年(1791年)に建立され、大きなつげの木が地蔵尊を覆っていたことから“つげの木地蔵”と呼ばれるようになりました。右,目白道、左,田無道、の道標があり、道案内にもなっていたようです。終戦間もない頃に本尊は盗まれてしまいましたが、昭和29年(1954年)に再建されました。
閲覧数34

大小二体が並んでいます。大きい地蔵は正徳5年(1715年)に建立され、小さい地蔵は年代不明です。白装束で夜中に祈願しながら小さい地蔵を倒すと、大きい地蔵は小さい地蔵を起こして貰いたいため、願い事をかなえてくれるという信仰が伝えられていて、昭和30年頃まで続いていました。
閲覧数44

上鷺宮の農家の人たちが大正11年(1922年)に創建し、武州御嶽神社、榛名神社、伊勢皇大神宮の三社が祀られています。神社の呼名は上鷺宮字北原の地名からつけられました。鷺宮八幡神社の祭禮の時は神酒所となり、神輿,山車が出入りします。
閲覧数64

現在の千川通りは昭和35年(1960年)に玉川上水の分水の千川上水を暗渠にして出来上がりました。千川上水は千川と呼ばれ、現在の五差路交差点辺りに、クズレ橋と呼ばれて、婚礼の行列は渡ってはいけないと言われた九頭竜橋が架かっていました。
閲覧数43

昔、親が深く信仰していた東伏見神社の神主様から「あなたの土地にお社を建てなさい」と言われ、東伏見神社の神主様によりご神体を祀りました。今でも変わらず、近所の人々が親しみを持ち、通る時にはお参りをしています。地域の人々を守ってくれる東伏見神社に感謝しています。
閲覧数21

若宮地区に「オリーブ橋」という橋があります。 由来は、白鷺1 丁目に昭和17 年から在住されていた作家の壺井栄さんの名作「二十四の瞳」はこの地で執筆され、そのご縁により香川県の野間小学校との交流が始まりオリーブ の木を12 本頂いたことによります。 その後、道路土地区画整理事業 計画の時に「オリーブ橋」と名付けられたものです。
閲覧数31
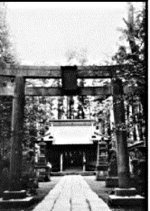
創建康平7 年(1064)。源頼義の建立が始まりとされ、鷺が多く棲んでいたため「鷺宮大明神」と称され、これが地名「鷺宮」の由来となる。正保2 年(1645)に八幡神社(通称、鷺宮八幡)と改称。8 月末例大祭で奉納される「鷺宮囃子」は江戸末期から始まり、中野区無形文化財に登録されている。
閲覧数55

妙正寺川は、水源は妙正寺池で中野区を流れ神田川に合流する。大正期頃までは流域の農業用水として利用されてきたが、昭和期以降西武鉄道開通から急速な市街地化が進み、氾濫も発生(最近では2005年)、鷺宮駅南西側では2013年に地下調整池が完成し、現在も護岸整備工事等が継続されている。
閲覧数52

明治13 年福蔵院内に「雙鷺小学校」創立。 昭和5 年に現在の場所に移転。昭和22 年中野区立鷺宮小学校と改称。平成20 年には北京市西単小学校と友好校となり、令和3 年に開校140 周年を迎えました。令和6 年4 月西中野小学校と合併し、中野区立鷺の杜小学校と改称しました。
閲覧数79

庚申塔は、庚申塚ともいい、道教に由来する庚申信仰に基づいて建てられた。江戸時代になると、庚申講を行う際に石碑や石塔を建てる風習が広がり、集落や街道沿い、寺社の境内など に多く見られるようになり村の名前や庚申講員の氏名を記したものが多い。これは笠付き庚申塔です。
閲覧数40

いまから547年前の1477年(応仁の乱後)、武蔵国多摩郡の江古田原および沼袋において合戦がありました。主戦場が哲学堂公園から新青梅街道沿いに下ったところにある江古田公園(松ヶ丘2-29)でした。この公園の一角に「江古田古戦場」という立派な史跡があります。中野区が昭和30年10月に建立したものです。
閲覧数113

源義家由来の八幡宮から創られたといわれる八幡神社。木造権現造り神殿が、昔懐かしい日本が広がる。現在の社殿は昭和3年に建造された。
閲覧数40

徳川幕府はキリスト教の侵略を恐れ、踏み絵などの厳しい制限を行った。山荘は切支丹屋敷ともいわれその取り締まりの拠点であった。寛永29年のこと
閲覧数34
全0件